第1話:ログアウトした世界の中で(冒頭)
朝が来るたびに、世界は忙しなく動いているように見えた。
駅に向かう人々の背中、タイムカードを押す音、鳴り止まない通知音。
――でも、僕の中だけ、何も動いていなかった。
奏は会社のデスクに座りながら、目の前のモニターに映る文字列をただ追っていた。いや、「追っているふり」をしていた。頭には何も入ってこない。忙しそうに資料を手渡し合う同僚たち、電話対応に追われる隣の席の女性、そのすべてが、自分とは異なる世界の出来事のように感じられた。
(なんで、こんなに足音が遠いんだろう……)
研修時代はまだよかった。皆が同じスタートラインにいて、失敗しても「大丈夫」と笑い合えた。でも部署配属されてから、他人のスピードに、自分の心がどんどん置いていかれた。
失敗したわけでもない。ただ、ついていけなかった。
人の目、業務量、評価、昼休みの会話。すべてが怖くなった。
ある日、会議室で上司に「大丈夫?」と声をかけられたとき、心の糸が切れた。
「……すみません。辞めさせてください」
自分でも驚くほど、声は穏やかだった。それから先の記憶は曖昧だ。荷物を整理した日、社員証を返した日。どれもまるで夢の断片のようだった。
誰とも連絡を取らず、ただ家に籠もり、昼夜を問わずゲームの世界にだけ生きるようになった。
「え? 奏が辞めた?」
その噂を耳にしたとき、悠真は書類を落としそうになった。
同期の中でも、口数は少なく目立たない存在だった奏。だけど研修で一緒になったとき、ふとした仕草や静かな表情が気になって、以来、すれ違うたびに目で追っていた。声をかけるタイミングを、何度も逃したまま。
まさか、もう二度と会えなくなるなんて――
(このままじゃ、何も始まらないまま終わる)
悠真は焦って、大学の同級生、共通の研修仲間、高校時代の友人……あらゆる繋がりを辿り始めた。スマホの連絡帳をスクロールし、深夜のSNSを巡回し、わずかな手がかりをかき集める。
数日後、「どうやら○○ってゲームに入り浸ってるらしいよ」という一文がLINEで届いたとき、悠真は迷わずそのゲームをインストールした。
操作方法もわからないまま、名前も設定も適当だった。
ただ「会いたい」一心で、ログインボタンを押した。
(もう、あの時みたいに――見てるだけなんて、絶対にしない)
キーボードの上を指が滑るたび、何度も「誤操作です」とのアラートが表示される。悠真は眉間に皺を寄せながら、ため息をついた。
「これ、マジで意味わかんないんだけど……」
仮想世界の中で自由に動けるどころか、メニューの開き方すらわからない。キャラクターはひょこひょこと同じ場所を行ったり来たりするだけで、NPC(ノンプレイヤーキャラ)にぶつかっては転び、間違って武器を投げ捨て、意味もなくジャンプする。
リアルでは「仕事も人間関係もそつなくこなす人」と言われることが多い悠真だったが、その器用さはゲームにはまったく通用しなかった。
――それでも、やめようとは思わなかった。
(ここに、奏がいるかもしれない)
そう思うだけで、何度エラーが出ようが、画面がバグろうが、やり直す気力が湧いてくる。
初めて彼を見かけたのは、ログインして3日目の夜だった。
フィールドの片隅、静かな森のエリアで。ベンチのような石の上に座り、ひとり黙って空を見上げている小柄なキャラクター。
名前欄に浮かぶのは、「SOU」。
――そのIDを、悠真はよく覚えていた。
送ってもらったメールで見かけたスクリーンショットに、同じ名前が載っていたのだ。「多分これ、奏だと思う」と誰かが送ってくれた、たった一枚の画像。
けれど本当に、そのSOUが目の前にいるとは――
(本当に……見つけた……)
鼓動が速くなる。目の奥がじんと熱くなった。ゲームの画面越しなのに、どうしようもなく胸がいっぱいになる。
それでも、すぐには声をかけられなかった。悠真のアバターは、ただSOUの隣に立ったまま、何も言えずにいた。
けれど数分後、SOUがこちらをちら、と見た。そしてぽつりと、画面にメッセージが表示される。
「何か用?」
たったそれだけ。けれど、悠真の指は震えていた。
「……ううん。そこの景色、綺麗だったから。隣、座っていい?」
その返事は少しだけ間があってから返ってきた。
「どうぞ」
その一言が、世界のどこよりも優しく響いた。
その日から、ふたりは毎晩、決まった時間にログインするようになった。
最初の頃、奏はあまり話さなかった。こちらが何を言っても、短い返事か、黙って頷くような相槌だけ。それでも、毎回決まった場所に現れて、悠真のアバターの隣に座ってくれた。
(誰かと繋がっていたい気持ちは、まだどこかにあるんだ)
悠真はそう感じて、焦らず、急がず、ただそばにいた。
ゲームのクエストにはほとんど進まず、ふたりでただ、森の中の小道を歩いたり、草原で昼寝をしたり、夜空を見上げたり。
ある晩、奏がふいに話しかけてきた。
「……初心者っぽい動きだよね、君」
「やっぱりバレてた?」
「うん。何度も同じところで転ぶし、攻撃の時に武器間違えてるし」
「うわ……恥ずかしい」
「……でも、なんか一生懸命で、ちょっと笑える」
(今……笑った?)
画面の向こうにいるはずなのに、悠真ははっきりと、その微笑みが想像できた。冷たく閉ざされていた彼の世界に、ほんの少し、光が差した気がした。
(あの日、声をかけられなかった俺に――少しだけ、挽回のチャンスをくれてる気がする)
この世界の中でなら、もう一度、彼と向き合えるかもしれない。
そんな希望を、悠真は初めて抱いた。


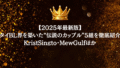

コメント