第7話:「信じたい、でも――」
休日の午後。
「ねぇ悠真、これ……似合う?」
奏が照れくさそうに差し出したのは、淡いブルーのシャツ。
休日のショッピングモールで、ふたり並んで歩く姿は、まるで何年も一緒にいる恋人のようだった。
悠真は微笑んで、シャツを奏の肩に当ててみる。
「うん、すごく似合ってる。爽やかで、君らしい」
「……そっか。じゃあ、これにする」
「俺が買うよ。今日の記念に」
「え、でも……」
「今日は、君が隣にいる記念日。だから、俺に買わせて?」
少し驚いたような顔をした奏は、やがて微笑みながら小さく頷いた。
「……ありがと。大事にする」
こんな穏やかな時間が、ずっと続けばいい――そう思った瞬間だった。
夕暮れ。帰り道の交差点。
信号待ちをしていた奏に、声がかけられた。
「……久しぶりだね、奏くん」
ふいに振り向いた先に立っていたのは、健吾だった。
優しげな笑顔の奥に、冷たいものが滲んでいる。
「あ……健吾さん」
「少しだけ、話せるかな。悠真くんのこと、君にちゃんと伝えておきたいことがあって」
健吾はあくまで柔らかく、だが有無を言わせない空気で奏を歩道の先へと誘導した。
カフェの個室。カーテンの隙間から、夕日が赤く差し込んでいた。
「ねえ、悠真くんのこと、どこまで知ってる?」
「え……?」
「彼、昔から独占欲が強くてね。一度手に入れたら、他のものは見えなくなるタイプなんだ。
人を縛って苦しめるの、得意なんだよ」
健吾の声は低く、静かで、どこか壊れかけたオルゴールのようだった。
「……嘘だ。悠真はそんな人じゃない」
奏は震える声で言い返した。でも、健吾の目にはどこまでも確信めいたものが宿っていた。
「彼に傷つけられた人、僕だけじゃない。――君も、いずれそうなるかもしれないよ?」
その瞬間、カップの中のコーヒーが波打つほど、心臓が強く脈打った。
夜。
奏はひとり、ベッドに座っていた。
手にしたシャツは、あのとき悠真が選んでくれたもの。だけど――健吾の言葉が、何度も頭の中でリフレインする。
(悠真を信じたい。でも……)
スマホを手に取り、メッセージアプリを開く。
そこには、毎日のように届いていた悠真からの「おはよう」「今日はどうだった?」という優しい言葉の数々。
奏は静かに目を閉じた。
(……本当に、あの笑顔を信じていいの?)


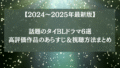

コメント